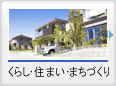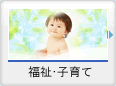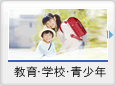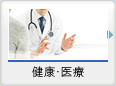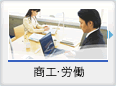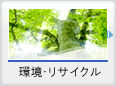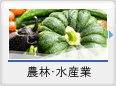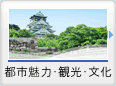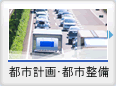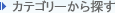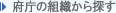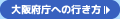健康医療部 薬務課 平成24年 入庁 【配属歴】 平成24年 健康医療部 薬務課
鶴村 春佳 Tsurumura Haruka
平成27年 茨木保健所 生活衛生室 薬事課
平成29年 健康医療部 食の安全推進課
平成31年 同 薬務課
薬学職を志したきっかけ、大阪府に入庁した理由を教えてください。
大学では薬学を学び、卒業後は臨床薬剤師として民間の調剤薬局に勤務していました。学生時代から志望していた仕事ができ、やりがいもあったのですが、将来のことを考えたとき、違った環境に身を置いてみたいと思うようになりました。
また、調剤薬局で働いていると、老若男女を問わず、本当にたくさんの方が医療機関を受診されるということに驚きました。病気の治療が大切であることは当然ですが、そもそも病気にならないためにはどうすればよいのだろうか、と予防医療の重要性について考え始めたことがきっかけで、公衆衛生を担う行政薬剤師という仕事に興味を抱きました。
そのようなときに、大阪府の薬学職の募集があり、縁を感じました。広域行政を担う大阪府という大きな組織で働くことに魅力を感じ、入庁しました。
入庁後に携わってきた仕事について教えてください。
入庁後はじめて配属されたのは、健康医療部薬務課です。ここでは、主に医療機器関連の事業者の審査や立ち入り業務を担当していました。
平成27年に茨木保健所に異動になり、医療機器や医薬品、麻薬に関することなど、幅広く薬事業務を担当しました。
平成29年には健康医療部食の安全推進課に配属され、食中毒や食品への異物混入、違反食品に関する業務等を担当し、平成31年から再び健康医療部薬務課に所属しています。
現在の健康医療部薬務課でのお仕事について教えてください。
現在所属のグループでは、医薬品や医療機器、化粧品、医薬部外品、再生医療等製品のメーカーや販売店などの審査業務を担当しています。これから製造したい、販売したい方を対象に、法律で定まった基準にのっとって相談を受け付け、許可に必要な審査を行います。申請者のもとに赴いて現地調査を行ったり、円滑な申請・手続きができるよう、講習会を開催し、説明を行うこともあります。
どういったところに仕事のやりがいを感じますか?
私の担当業務のひとつとして、大阪府では薬事審議会を設置しているのですが、そのなかの部会のひとつである「医療機器安全対策推進部会」の事務局を担当しています。この部会では医師や看護師、臨床工学技士など様々な職種の方の意見を伺いながら、医療機器の適正使用を推進し、安全性を確保するための施策について審議しています。全国的にも薬事関連部署が医療機器の安全対策に取り組んでいる自治体は少なく、貴重な経験をさせていただいており、やりがいを感じています。
前職とのギャップは感じますか?
現在は慣れましたが、最初は戸惑うこともありました。調剤薬局の場合、開局時間内に来られた患者さんにお薬をお渡しして、薬歴を書いて退勤、としていたため、どちらかといえば今日はここまで、と区切りをつけやすい仕事でした。行政の仕事にも期限はもちろんありますが、今日中にやるべきなのか、明日でも良いのか、期限の切り方がわかるまで少し時間がかかり、より自分で自分をマネジメントする能力が求められる職場だと思いました。
薬学職が働く職場の雰囲気について教えてください。
薬務課全体で50名ほどの職員がおり、私が所属するグループには11名が在籍しています。年齢もバランスよく、新規採用の若い職員もいます。基本的に各自の担当業務がありますが、例えば隣で電話をしている同僚が困っていれば、助け船を出すなど、協力し合う雰囲気もあると思います。
また、課内には私以外にも民間から転職してきた職員も複数おり、新卒で入庁した職員だけでなく、転職し入庁してくる方にも、馴染みやすい環境だと思います。
薬学職の上司や先輩から学んだことはありますか?
わからないことにぶつかったとき、まずは自分自身で一旦調べたり、考えたうえで、自分の意見を伝えることです。上司や先輩は経験が豊富で、私が知らない正解をご存知のことも多くありますが、いきなり正解を聞いてしまうと自分の勉強にならないし、納得できないこともあるかもしれませんので、わからないなりにも自分の考えをもって「私はこう思う」と伝えてみることが大切だと思っています。例えその考えが間違っていても、しっかりと訂正していただけます。
これまでのキャリアの中で、最も苦労したことについて教えてください。
薬事監視員として薬務課に配属されて以来、本庁と保健所で5年間勤務しましたが、部内の交流人事の一環として、食の安全推進課に配属されたときは、これまでとは全く畑違いの仕事をすることとなり、不安になりました。
2年間という期限付きではありましたが、同じ部内であっても、食の安全推進課と薬務課ではローカルルールが異なるというか、業務の進め方が異なる部分もあり、当初は戸惑うこともありました。
しかし、働く場所や管轄する法律、対象が変わったとしても、「郷に入っては郷に従え」と考えられたことと、行政薬剤師としての基本は許認可や監視指導、啓発活動であり、大きくは変わらないのではないかと思えるようになったことで、適応することができました。
この2年間の経験によって、勤務場所が変わってもやっていけるのではないか、という自信がついたと思います。
これまでのキャリアの中で、どのようにスキルを伸ばしてきましたか?
入庁後すぐに新規採用者全員が参加する研修を受け、配属が決まったあとはジョブトレーナーである先輩について業務の流れを覚えていきました。また、1年目、2年目と年次で区切った研修にも参加しました。
また、行政の職員になったとはいえ、自分が薬剤師であることには変わりありません。薬剤師向けの研修会が開催されていれば参加したりと、薬剤師としての考えや姿勢を忘れないようにしています。
仕事をする上で、心がけていることを教えてください。
許認可や監視指導を行う上で、その根拠を自分なりに調べて、理解しておくことが大切だと思っています。窓口や電話で対応する際も、法律をもとにした根拠をしっかりともっていれば、相手方が求めていることを読み取り、適切な回答ができるようになります。
また、基本的には組織として業務を遂行していきますが、かといって上司や先輩に頼りきりになるのではなく、自分自身の仕事に責任をもつ姿勢が大切だと思っています。
今後、大阪をどのような街にしていきたいと思いますか?
府民の皆さんに、安心して日常生活を送っていただくことが、私たち健康医療部の最大の目標であり、使命です。薬や医療機器関連の業務にしっかりと取り組むことが、府民の皆さんの生活の安心・安全を守ることにつながると考え、努力をつづけていきたいと思います。
これから大阪府で働くことを考えている読者にメッセージをお願いします。
就職活動をされている薬学生や薬剤師の方は、臨床現場やメーカーでの勤務を第一に考えているかもしれません。しかし、行政薬剤師は実に幅広い仕事であるということをまずは知っていただきたいと思います。大阪府の場合、薬学職は薬事、食品、環境、検査のいずれかの分野に配属されますが、どの分野でも臨床現場やメーカーでは経験できないような仕事ができるはずです。幅広い業務を覚える大変さはありますが、「多くのことを知りたい」「チャレンジしたい」と考える方にはぴったりの環境です。ぜひ行政薬剤師という選択肢に目を向けて、チャレンジしていただきたいと思います。
9時00分 メールと新聞のチェック、予定確認 |  |
※掲載されている職員の職務内容、所属及び所属名称は配属当時のものです。
このページの作成所属
人事委員会事務局 人事委員会事務局任用審査課 任用グループ
ここまで本文です。

 府庁の組織から探す
府庁の組織から探す