ここから本文です。
【平成13年度】 環境の状況並びに豊かな環境の保全及び創造に関して講じた施策に関する報告(概要)
2001年度【平成13年度】
1.おおさかの環境
激甚な産業型公害は克服!
大気中の二酸化硫黄(So2)や河川・海域(大阪湾)のシアン、カドミウム等は環境基準を達成できており、克服できたものと考えます
公害の態様の変化により、都市生活型公害の解消が課題
自動車排出ガスが主な原因とされる大気中の二酸化窒素(No2)や浮遊粒子状物質(Spm)、また、生活排水が主な原因とされる河川や海域の有機物汚染(Bod・Cod)は、いずれも改善の傾向にあるものの、環境基準を達成できていない地域が残っています
その他にも府域には解決しなければならないさまざまな環境問題があります
廃棄物の不法投棄や野積みなどの不適正処理、地球温暖化や都市部のヒートアイランド現象、さらにダイオキシン類や環境ホルモンによる人や生態系への影響など、解決していかなければならないさまざまな問題を抱えています
おおさかの環境をより良くするために
おおさかの環境をより良くするために、わたしたちのおおさかをもっと住みやすくするために、さまざまな環境問題を一つひとつ改善していく必要があります
大阪府では、平成14年3月に新しい環境総合計画である「大阪21世紀の環境総合計画」を策定しました

キーワードは循環型社会をめざした環境都市づくり
今後の方向は
- 21世紀に残すことになった環境上の負の遺産を解決します
- 「循環型の社会づくり」をめざします
- 府民、事業者、環境NGO・NPOそして行政がパートナーシップをもって推進していきます
新しい環境総合計画では長期的な目標である「豊かな環境都市・大阪」の構築に向け、6つの主要課題を設定しています
- 廃棄物の減量化、リサイクル、適正処理などの「資源循環」
- 河川や大阪湾の水質や水量、親水空間などの「水循環」
- 温室効果ガスによる地球温暖化などの「地球環境」
- 自動車による大気汚染などの「交通環境」
- ダイオキシン類などの排出抑制、自主管理などの「有害化学物質」
- 都市と自然が共生する魅力ある地域づくりなどの「自然環境の保全・回復・創出」
2.資源循環 【廃棄物の減量化・リサイクル・適正処理など】
産業廃棄物
産業廃棄物の排出量は年々減少傾向にあり、これに対して再生利用(リサイクル)率は上昇傾向にあります。しかしながら、平成12年度の産業廃棄物の排出量1,768万トンのうち、リサイクルや減量化された残りの147万トンが最終処分されており、最終処分場の残容量を圧迫する状況にあります。
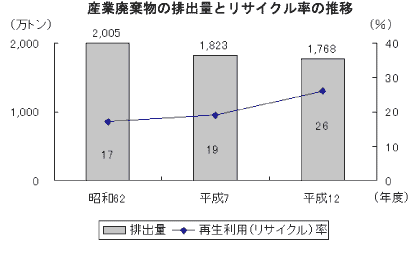
また、府内には、不法投棄や野積みなどの産業廃棄物の不適正処理が依然として増加の傾向にあり、特に行政の監視が手薄になる夜間や早朝、休日に、きわめて短期間に行われるなど、その手口が悪質・巧妙化しています。
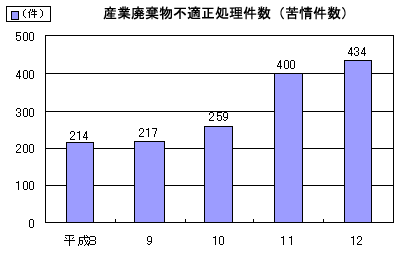
ごみ(一般廃棄物)
一般廃棄物の排出量も、年々減少傾向にありますが、1人1日あたりの排出量は1.3kgで、全国の1.1kgに比べると多く、また、リサイクル率は上昇傾向(大阪府8.3%)にありますが、これも全国(13.1%)に比べるとまだまだ低いのが現状です。
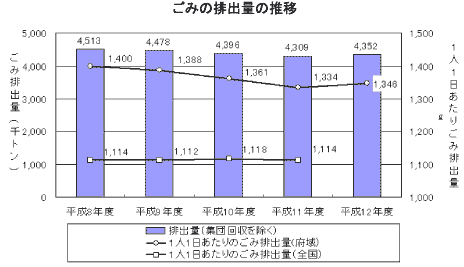
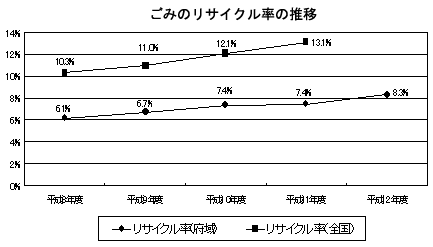
平成13年度に講じた施策
- 大阪府廃棄物処理計画を策定しました。
- 容器包装・食品・家電・建設リサイクル法に基づくリサイクルを推進しました。
- 下水汚泥、水道残渣、建設副産物、剪定枝のリサイクルや有効利用に努めました。
- ごみの減量化やリサイクルを推進する「エコショップ」制度を普及させました。
- 不適正処理に対する監視パトロールを集中して行いました。
- 野積み、野焼き業者を検挙し、排出事業者に対して撤去の措置命令を出すなど不適正処理の撲滅に努めました。
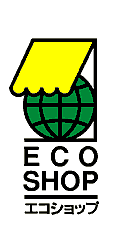
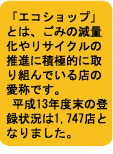
産業廃棄物不適正処理を防止するための監視パトロール隊による出発

廃棄物処理対策について
大阪府廃棄物処理計画に基づき、廃棄物の最終処分量を平成22年度までに概ね半減させることをめざして、廃棄物の発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再生利用(Recycle)(3Rといいます)を、さらに推進します。
また、大阪都市圏における循環型社会の構築を図るため、廃棄物の最終処分場跡地等を活用し、民間事業者を主体としたリサイクル施設の整備や自然とふれあう場「共生の森」を創造する「大阪エコエリア構想」を策定します。
3.水環境 【河川や大阪湾の水質や水量、親水空間など】
河川の環境
川の汚れ具合を示すBod濃度は、改善の傾向がみられます。大阪市内でもっとも汚いと言われてきた寝屋川に、ギンブナやモツゴなどの魚が戻ってきたとの報告もあります(大阪市生息状況調査)。

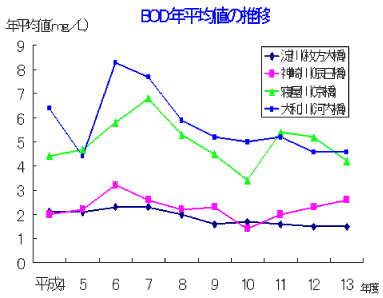
海の環境
海(大阪湾)の汚れ具合を示すCod濃度の改善は依然として進んでおらず、環境基準の達成率は50%に満たないのが現状です(47%)。主な原因は、生活排水対策の遅れに加えて、海底のヘドロの堆積にあると考えられます
平成13年度に講じた施策
- 下水処理水を高度処理し、散水及び水路浄化へ利用しました
- 下水道や合併処理浄化槽の普及促進に努めました
- 西除川、東除川及び音川で河川水の直接浄化を実施しました
- 安威川、天野川、石川等において、市町村や地元自治会、NPO等の協力を得て、清掃活動を実施しました。
生活排水対策について
平成12年度の汚水処理率は81.2%で、旧計画の目標である100%を達成できませんでした。
このため、新しい環境総合計画では、新たに地域の実情に応じた実施計画を策定し、平成22年度までに生活排水の100%処理をめざします。

4.地球環境 【温室効果ガスによる地球温暖化など】
CO2の排出量
平成11年度の二酸化炭素の排出量は、電力や鉄鋼業の稼動が低下したことにより、産業部門からの排出量が減り、京都議定書の基準年度である平成2年よりも0.8%削減されています。しかしながら、運輸、民生部門の排出量は、増えており、京都議定書の約束達成のためには、これをどう減らしていくかが大きな課題となっています
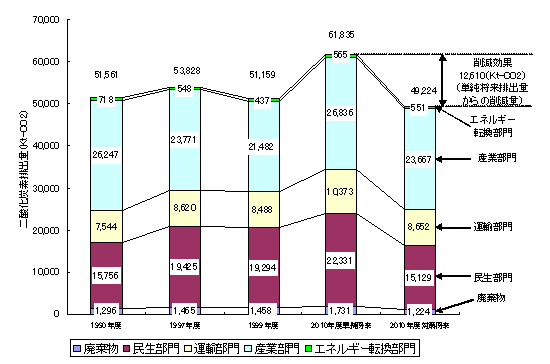
平成13年度に講じた施策
- ESCO事業による省エネ化を推進しました(府立母子保健総合医療センター)
- 村野浄水場や安威川流域下水道中央処理場、食とみどりの総合技術センターに太陽光発電設備を設置しました。

村野浄水場太陽光発電設備
- グリーン商品や買い物袋持参を呼びかける「グリーン購入/No!!包装キャンペーン」を実施しました。府内のスーパー・百貨店2,584店舗の協力を得ました。

地球温暖化対策について
温室効果ガスを平成22年度までに基準年度である平成2年度から9%削減させることをめざして、新エネルギーの導入や省エネルギー化の推進のほか、各主体の自主的な取り組みの促進に努めます。
5.交通環境 【自動車による大気汚染など】
二酸化窒素濃度
大気中の二酸化窒素の年平均濃度は横ばいの状況ですが、環境基準の達成率はここ数年、改善の傾向にあります。
| 一般大気環境測定局 | 96% |
|---|---|
| 自動車排出ガス測定局 | 68% |
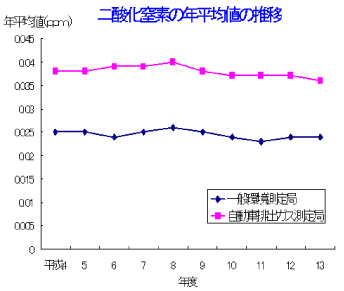
浮遊粒子状物質濃度
浮遊粒子状物質については、年平均濃度は改善の傾向にありますが、環境基準の達成率はかんばしくありませんでした。(高濃度が2日続いたことによる)
| 一般大気環境測定局 | 44% |
|---|---|
| 自動車排出ガス測定局 | 32% |
平成13年度に講じた施策
- 低公害車や低排出ガス車(Lev-6)といった低公害な車の普及(購入の際の優遇税制、燃料供給施設の整備、貨物輸送を行う事業者への低公害車代替のための助成など)に努めるとともに、府の公用車への率先導入を図りました。

- 交通需要マネジメント(TDM)施策の一環として、国道170号区間おいて公共車両優先システムを導入するとともに、公共駐車場、大型商業施設の駐車場を活用した「パークアンドライド」を府内15か所で実施しました。
自動車排出ガス対策について
平成22年度末までに二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準の概ね達成をめざして、「大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画」を策定し、低公害な車の導入やディーゼル車対策等を推進します。
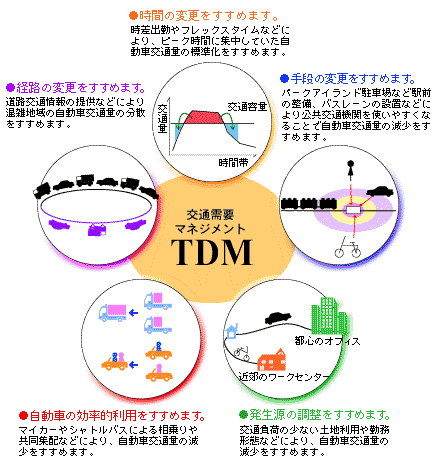
6.有害化学物質 【ダイオキシン類などの排出抑制、自主管理など】
平成13年度に講じた施策
- 能勢町のダイオキシン類汚染土壌の浄化に向けた環境整備を進めました。
- 平成14年12月に規制強化されるダイオキシン類の規制基準を遵守するよう指導を徹底しました
- Prtr法の全面施行(平成14年度)を前に、大阪府化学物質適正管理指針に基づき、使用量等の実態把握を行うとともに、事業者による自主管理の促進に努めました。
Prtr(Pollutant Release and Transfer Register)は、有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは、廃棄物等に含まれて事業所外に運び出されたかというデータを事業者自らが把握し、集計し、公表する仕組みのことです。
7.自然環境の保全・回復・創出 【都市と自然が共生する魅力ある地域づくりなど】
おおさかには緑が少ないと言われますが、府域は「天与のグリーンベルト」と言われる北摂山系、金剛生駒山系及び和泉葛城山系の3山系に囲まれ、豊かな自然・歴史・文化に恵まれています。
府域に生息する貴重な生物
府域には1万種を超える生物が生息・生育していると予想され、中には、北摂山系に棲む特別天然記念物のオオサンショウウオや淀川のわんどに棲む天然記念物のイタセンパラなどもいます。

イタセンパラ
淀川には、多様な水生生物の生息や繁殖地となっているわんどがあります。しかしながら、わんどの数は500個程度ありましたが、現在は50個程度に減少しており、密漁等に対するパトロール等の保護活動を行っています。

淀川のわんど
都市部のみどり空間
都市部のみどり空間は少なく、都市公園の整備を進めていますが、府民1人あたりの公園面積は4.8平方メートルと全国平均の約半分となっています。また、この10年で、都市公園面積は860ha増加しましたが、逆に森林面積は840ha、農地面積は2,800ha減少しています。
平成13年度に講じた施策
- 大阪府立自然公園条例に基づき、府立北摂自然公園を指定しました。
- 槇尾川や金熊寺川などにおいて、生態系に配慮した川づくりを行いました。
- 信太山湿地等を対象に、土砂のしゅんせつ、乾燥地植物の除去等の保全対策を講じました。
- 農業用水やため池において親水施設等の整備を行いました。
- 緑化樹7万本を無償配付し、民間施設や公共施設の緑化を推進しました。

信太山湿地保全事業
みんなでおおさかの自然を守り、つくる
豊かな海は豊かな森によって育まれるという考えのもと、漁業者自らが森づくりを行う「魚庭(なにわ)の森づくり」活動を支援しました。

魚庭(なにわ)の森づくり
- 多様な生態系の保全や洪水調整などの重要な役割を果たす棚田を守るため、「棚田・ふるさと保全基金」を運用して、府民ボランティアと地元農家が一体となって、棚田保全活動を行いました。
- 水とふれあう快適な水辺環境をめざし、長瀬川水路(農業用水路)等において、水路の景観整備と併せて遊歩道や親水施設、緑化などの総合的な整備を行いました。
- 岬町長松自然海浜保全地区において、生物観察や海浜清掃を行う「なぎさの楽校(がっこう)」を開催しました。

- 地域の緑化や美化を地元自治会や企業等の団体が、府や市町村と協力して行うアドプト・プログラムを、道路だけでなく河川においても試行的に実施しました。
